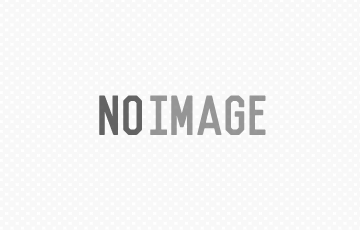※この記事はみすてむず いず みすきーしすてむず その2 Advent Calendar 2024
およびフリーランス・個人事業主 Advent Calendar 2024の4日目です
アドベントカレンダー書くぞと言ったものの、忙しかったのもあり大したネタも思い浮かびませんでした。
そういえばそろそろITエンジニアとしても、フリーランスとしてもそれなりの長さの歴になってきたので、今年1年だけではなくてフリーランスとしての過去を振り返ってみようと思います。
あ、今日12/4は誕生日です。
生年月日はギャル曽根さんと同じです。
経歴
2009年、新卒でメーカー系子会社SEに
2013年6月、転職してSESの会社へ
2016年6月、フリーランスに
2019年12月、フリーランスから法人化
という感じです。
法人の設立日は誕生日です。
別に名前とかプロフィールとかは特段隠してないので個人的な経歴についてはLaprasの公開プロフィールを貼っておきます
ITエンジニアとしてはAWS周りをあれこれやってます。
インフラ設計、実構築、既存構成改善など。
IaCもやるし、スキルトランスファーやったり壁打ちしたりもしてます。
最近はAPI作ったりもしてます。
2013年に転職して最初の案件で、当時としてはまだ流行り始めたかその前かぐらいだったAWSに触れて、今後はAWSの時代が来ると思ったのでそこからどっぷりです。
その前はオンプレのアプリ運用をやっていたのと、前述のように当時はクラウドインフラがまだあまり一般的ではなかったのでそのギャップに衝撃を受けましたね。
2016年にフリーランスになったのは色んな理由がありますが、SESをそのままやるならフリーランスでもあんまり変わらないかなと思ったのと、1つの会社にずっと長くいるイメージがあまり沸かなかったというのが一部としてあります。(これで全部ではないです)
今年某イベントで同じようにフリーランスでやっているITエンジニアの人が集まる機会があったのですが、意外とここ3〜4年でフリーランスになられたという方が多く、その中では自分はかなり古参なほうでした。
確かに当時はまだ今よりは情報がなかったですね。
フリーランスになってみて
フリーランスってどうなのみたいなのは、なったことない人からは気になるところだと思います。
なったときは割と適当で、青色申告承認申請をするのを忘れて初年度が白色申告になってしまったりしましたが、何とかなりました
今は当時と違って情報がたくさんあるので、なる時に何するのみたいなのはちゃんと調べましょう
例えば以下など
会社を辞める前に要確認!フリーランスになるために必要な手続きまとめ
案件はどうするの
フリーランスは直接営業して仕事取ってナンボという意見がネットではあります。
とはいっても、自分の場合エージェントから仕事をもらうのが基本なので、お金周りを自分でどうにかするところ以外、働き方自体はそんなにSESの会社にいた頃と変わりません。
自社から仕事もらうのがエージェントからだったり直接だったりに変わっただけですね。
ただし、独立前にエージェントと話をして、今のスキルで仕事が取れるのかはちゃんと測りましたね。
もちろんそれができるならやればいいですが、別にエージェントからもらうことも悪くはありません。
自分のエージェントの使い方はちょっと特殊で、特定の会社からもらい続けるよりも、継続的にいろんなエージェントさんの案件を見て、案件を変える時に比較検討する、みたいなやり方でやってました。
今は本当にエージェントの会社が増え、それぞれに強みがある感じになっています。
自分の場合はAWSに強いエージェントさんと仲良くさせてもらっているつもりです。
…まあ、自分も直接どこかから仕事もらえないかなと思うときもあるのでそのための方策は常に探っていますが、それができなければエージェントに頼ることも恥じなくていいですよという話ですね。
むしろ自分とエージェント双方がWin-Winになれるようにしたほうが建設的でしょう。
もちろん、業務委託で準委任契約の案件をもらうばかりがフリーランスとしての働き方じゃないので、開拓して受託開発の案件をやったり、クラウドソーシング(お薦めはしませんが…)をやったり、いろんな形があっていいですね。
ただいざというときにはエージェントさんに話を通しておくとスムーズです。
お金周りどうしてるの?
多分多くの人が気になるのが、「フリーランスって自分で税金納めたり社会保険料払ったりの手続きが大変なんじゃないの?」だと思います
これに対する回答は「楽ではないけど、そこまでめちゃくちゃ大変ではない」です。
個人事業主であれば、概ね以下に気をつければなんとかなると思います
- 今まで会社が払っていた税金や保険料を自分で払う
- 住民税
- 年4回支払いが発生します。
- 所得税
- 確定申告で所得を申告後に支払い。場合によっては還付になることもある
- 消費税
- 課税事業者の場合(今だとインボイス制度のため少額でも課税事業者かも)
- 社会保険料
- 個人事業主の場合、国民健康保険料
- 7月〜翌3月に支払いが発生
- 会社員だったころの健康保険組合をお金払って継続も出来たはず(うろ覚え)
- 住民税
- 確定申告をする
- 所得額を確定し、支払う所得税・消費税額も確定する
その他個人事業税もありますが、ITエンジニアの場合発生しないことがほとんどです。
以下も参考になります
個人事業主が払う税金はいくら?計算方法と節税のポイントを解説
前提として、ITエンジニアのフリーランスは何かを仕入れて物を売るのではなく、技術・知見や労働力(という表現が正しいか微妙ですが便宜上そう書きます)を提供したり、ソフトウェアを開発して納品した対価としてお金を得るなどが一般的です。
仕入れが発生しないというのが結構大きなポイントで、そんなにめちゃくちゃ経費が発生するわけではありません。(経費にできるとされているもの、みたいなのはあれこれありますが、長くなるのでここでは省略します)
ただ、そうは言ってもあれこれ領収書を取っといたり、保険や寄付金控除周りのはがきを保存して使ったりとかは必要なので知識は必要ですが、一度やってしまえば流れがなんとなくつかめるかなと
面倒なら仕訳まわりは税理士さんに全部お願いすることもできなくはないです(その分お金はかかる)
迷ったらとりあえず領収書はもらっておいて、後から経費にできるか考えてもいいでしょう。
一応、MFクラウドやfreeeなどを使えば、自分ひとりの分ぐらいならなんとかなると思います。
仕訳を楽にするために個人事業の決済用のクレカを作っておくと何かとスムーズです(1敗)
よくわからないところは税務署や確定申告コーナーで相談することもできます。
ああ、あとよくある「フリーランスは会社員の1.5倍稼がないと〜」はITエンジニアのフリーランスではそんなに経費がかからないという前提が無視されているのであまり参考にしなくてよいです。
生存戦略・出口戦略は考える必要がありますけどね。
注意点
書いてあることと重複しますが、自分で払うお金が多いので、入ってきたお金をうっかり使いすぎると支払いの時に困ります。
また、健康保険が国民健康保険になるので、売上が上がってくると結構高くなります。
あと、年金ですね。
会社所属だと厚生年金として会社と折半で年金支払をしていましたが、個人事業主だと会社分がなくなるので将来もらえる年金が減ります(そもそももらえるのか、みたいな話はスコープ外なので触れません。)
他には、個人事業主だと会社と違って無限責任になります。
後述しますが、ある程度の規模があることをやりたい時はそういう意味でも会社を作ることをおすすめします。
※もちろん見込みが立つ前に会社を作っても損するだけなのでやめましょう
法人化してみて
まずなぜ法人化したのかとなると、自分の場合は消費税の支払い開始を先延ばしするためです。
今はインボイス制度があるのでいきなり課税事業者から始める人もいそうですが、それ以前は開業から2年以内、または売上1000万円以下であれば非課税事業者のままでよく、売上が1000万円超えた翌々年から消費税の支払いが発生するのですが、法人成りすることで法人の開設から2年間はまた消費税の支払いを先延ばしにできたので、そこを目安にしてました。
自分の場合は上記の理由でしたが、法人化する理由は様々なので必ずしも売上が基準ではありません。
売上がそこまでなくても、一定の目処が立っているなら早めに法人化して法人としての信用を貯めていくという考えも大アリですし、個人事業主の無限責任から会社の有限責任にするというのもあります。
また、対会社でないと話せない会社もあったり、資金調達のやりやすさも個人とはだいぶ変わります。
小規模法人向けの融資なんかもあります。
個人事業の頃と変わったこと・変わってないこと
実際のところ何が変わったかという話ですが、仕事のやりかた自体は変わっていません。
それはそうですね。個人事業でやっていたことを法人でやっているだけなので。
ただ、個人事業のころはあくまで個人で売上を所得として得ていたのですが、法人としてやるのであれば、売上を上げるのは法人であり個人とは別人格になります。
法人が売上として貯めたお金を個人に給与(自分の場合は役員なので役員報酬)として渡すというのが基本的な方法で、給与は会社にとって損金(経費にできる支出)となります。
初年度は役員報酬の設定をミスり、個人の側に全然金がないみたいになってしまったのでここは注意しましょう(役員報酬は年に1回しか決定できず、途中変更すると損金にできなくなってしまうので高すぎても安すぎてもダメでここはちょっとムズい)
また、個人では確定申告だけやっていましたが、決算周りの会計はさすがに自分では無理だなと思ったのでここから税理士さんにお願いしています。
ややトラップなのですが、税理士さんの職務範囲は基本的に税金・会計周りのところで、会社には他に社会保険周りの手続きや処理が必要になってきます。
分野的には社労士さんが扱うところですね。ここは個人事業と大きく違うところです。
給与改定したり、もし人を増やしたりなどしたときには手続きが必要なので、社労士さんや年金事務所に聞きながら対応しましょう。
(年金事務所に聞くとあれこれ丁寧に教えてくれます)
自分一人だし労務周りそんなにやることないけど、困ったときだけ聞きたい、みたいな需要だと、今ではスポット社労士くんみたいなサービスもあるので活用するといいと思います。
やってはいけないこと
全部を挙げることはできないので気をつけてほしいこととして。
個人と法人は別人格と書きました。
では、個人の方で案件Aを受けて法人のほうで案件Bを受ければ売上が分散できて課税額も減るよね、と思った方がいるかもしれませんが、これはやってはいけません。
同種の仕事を個人と法人で分けて受ける行為は租税回避行為とみなされかねず、最悪追徴課税されます。
たとえば、個人では執筆の仕事、法人では業務委託の稼働案件を受けるなど別の仕事をやるならそれには当たらないそうです
この辺のライン引きの細かいところはさすがにわからないので、鵜呑みにせず必ず税理士さんや税務署に確認しましょう
これから
ぶっちゃけ節税のために作った会社ではありますが、せっかく作ったのと、自分の身ひとつでできることに限界を感じ始めてきたので、そろそろ人と一緒に何かやったり、もうちょっと売上がスケールするものをやるべきかなとも思っています。
直近ではお金を貯めながら自分の出来ることを増やしてチャンスに備える、というのを続けていくのは変わらないですね。
ITエンジニアとしてどうするかはあんまり書きませんでしたが、そっちのほうも今まで得たものをあれこれ色んなところに還元したいなという思いもあるので、やれることを探っていきたいですね。
めっちゃ突貫で書いたので、変なとこあったらツッコミお待ちしています。